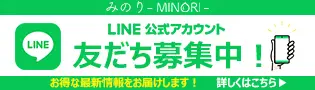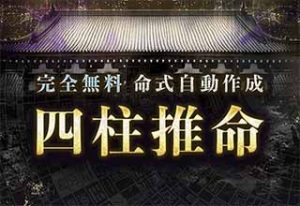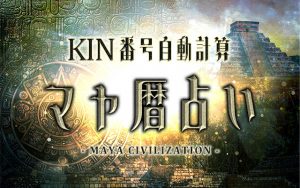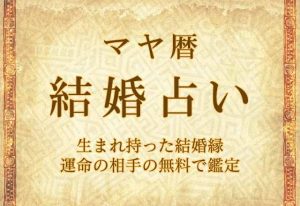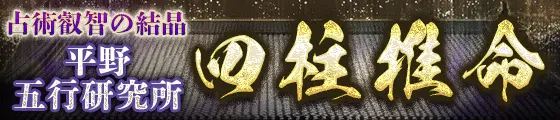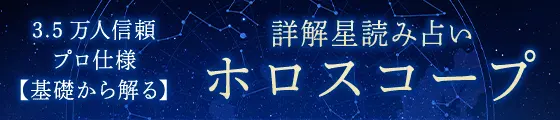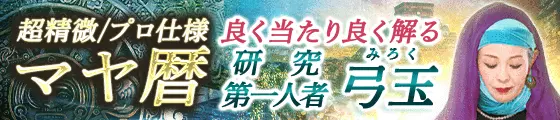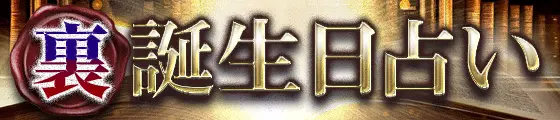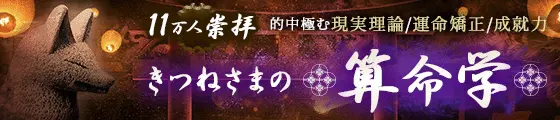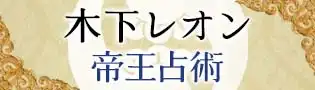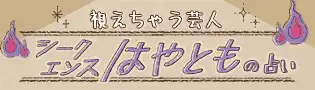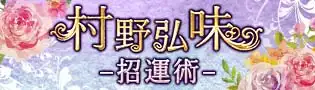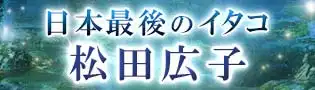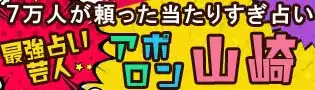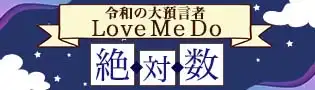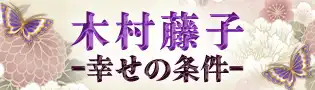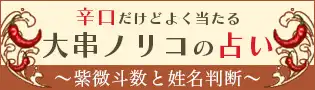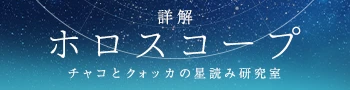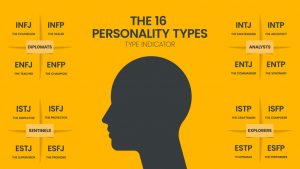五行思想とは?
五行とは、宇宙に存在するあらゆるものが「木・火・土・金・水」の五つの要素から成り立っているという思想で、陰陽思想と並んで東洋哲学の基盤を成す重要な概念です。この思想は春秋戦国時代(紀元前770年~紀元前222年)に体系化されたとされていますが、陰陽と同様に、より古い西周の時代に起源をもつとも考えられています。
「五行」の「行」という字には「巡る」といった意味があり、5つの要素が互いに循環し影響し合うことで、自然や社会の現象が生まれ、発展していくという考え方が根底にあります。
なぜこの5つの要素が選ばれたのかというと、いずれも人間が生きていく上で欠かすことのできない自然の恵みであり、当時の人々が自らの力で獲得しなければならなかった、生命に直結する要素だったからです。
五行の象意
ここでは、五行を構成する5つの要素、「木」「火」「土」「金」「水」が象徴する意味について解説します。五行の思想においては、これらの要素が持つ順序や流れが非常に重要であり、「朝から昼、昼から夜へ」と時の巡りや、「春から夏、秋、冬へ」といった季節の移ろいとも深く結びついています。以下に、それぞれの要素が示す象徴を紹介します。
| 五行 | 意味 |
|---|---|
| 木 | 朝の光、そして春の息吹。生命が芽吹き、草木が勢いよく伸びるような、成長と発展の象徴です。木は根を張り、大地にしっかりと立ち、風雨に耐えてそびえ立ちます。 |
| 火 | 燃え上がる炎と、その熱がもたらす力。昼の太陽が照りつける夏の光のように、情熱や活動を象徴します。火は物を変化させ、勢いと拡散の性質を持ちます。 |
| 土 | 全てを育む大地。日差しを浴びて生命を支え、作物を実らせる母のような存在です。収穫を迎える土地の豊かさや、山岳の厳しさもこの要素に含まれます。 |
| 金 | 秋の澄んだ空気と、沈みゆく夕陽の光。冷たくも美しく輝く金属のように、硬さと柔らかさ、洗練と収束の象徴です。整然とした静けさを帯びています。 |
| 水 | 夜の静寂と、全てのものが眠りにつく時。小川のせせらぎから大河のうねり、そして深く静かな海へ。水は流れ、蓄え、そして時に荒れ狂う、潜在的な力と陰の世界を表しています。 |
| 五行 | 五臓 | 五腑 | 五官 | 五腔 | 五主 | 五労 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木 | 肝 | 胆 | 目 | 鼻 | 筋 | 歩 |
| 火 | 心 | 小腸 | 舌 | 目 | 血脉 | 視 |
| 土 | 脾 | 胃 | 口 | 皮膚 | 肌肉 | 坐 |
| 金 | 肺 | 大腸 | 鼻 | 口 | 皮毛 | 臥 |
| 水 | 腎 | 膀胱 | 耳 | 耳 | 骨 | 立 |
五臓 … 五行に対応する臓器
五腑 … 五臓に対応する腑
五官 … 五行に対応する臓器
五腔 … 五行に体の内部
五主 … 各臓器と関係が深い身体の器官
五労 … 各臓器に悪影響を与える動作
| 五行 | 五色 | 五音 | 五味 | 五方 | 五季 | 五志 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木 | 青 | 角 | 酸 | 東 | 春 | 怒 |
| 火 | 赤 | 微 | 苦 | 南 | 夏 | 喜 |
| 土 | 黄 | 官 | 甘 | 中央 | 土用 | 思 |
| 金 | 白 | 商 | 辛 | 西 | 秋 | 憂 |
| 水 | 黒 | 羽 | 醎 | 北 | 冬 | 恐 |
五色 … 五行に対応する色の分類
五音 … 五行に対応する音
五味 … 五行に対応する味
五方 … 五行に対応する方角
五季 … 五臓が属し活発になりやすい季節
五志 … 五臓が病変をもたらす感情
五行の「相生」「相剋」「比和」
五行を構成する「木」「火」「土」「金」「水」の5つの要素のあいだには、「相生(そうじょう)」「相剋(そうこく)」「比和(ひわ)」という3つの関係性が存在します。これは、ある要素が他の要素にどのような影響を与えるか、助け合うのか、打ち消し合うのかを示すものです。
これらの関係性によって、五行思想は自然界や人間社会のあらゆる現象、全ての物事の生成・発展・循環・調和などを体系的に説明してます。ここでは3つの関係性がどんな意味を持っているのかをそれぞれ紹介していきます。
相生は、五行の1つが別の五行を生み出し、互いに助け合う関係を指します。たとえば、「木」は「火」を生じ、「火」は「土」を生じ、「土」は「金」を生じ、「金」は「水」を生じ、そして「水」は再び「木」を生みます。このように、五行は円を描くように循環しながら、お互いを育んでいくのです。
季節が春から夏、夏から秋へと順に移り変わるように、「木 → 火 → 土 → 金 → 水 → 木」という流れで、五行が自然のリズムに沿って進行する関係が「相生」です
★ 木生火(モクショウカ)
★ 火生土(カショウド)
★ 土生金(ドショウキン)
★ 金生水(キンショウスイ)
★ 水生木(スイショウモク)
相剋は、五行の1つが他の五行を制御したり、打ち消したりする関係です。これは互いに害を及ぼすようにも見えますが、バランスを保つための調整作用とも言えます。「木」は「土」を剋し、「火」は「金」を剋し、「土」は「水」を剋し、「金」は「木」を剋し、「水」は「火」を剋す。このように、五行は星型の構造を描くようにして、抑制し合う関係を形成します。
一般に相剋は「凶」の関係とされますが、「剋する」という行為は、単なる攻撃ではなく、制御や作用という意味でもあります。つまり、剋する側から剋される側へ、ある種の働きかけが起きているのです。
★ 木剋土(モクコクド)
★ 火剋金(カコクキン)
★ 土剋水(ドコクスイ)
★ 金剋木(キンコクモク)
★ 水剋火(スイコクカ)
比和は同じ五行同士が互いに共鳴し合う関係で、力を強め合う働きを持ちます。たとえば「木」と「木」、「火」と「火」など、同質のエネルギーが重なり合い、性質がより強く表れます。
相生・相剋・比和の関係において重要なのは、これらの関係が決して「絶対」ではないという点です。たとえば、ある五行が別の五行を生じる(相生)とき、それは力を与えると同時に、自らの力を削るという側面も持ちます。また、「剋する」関係も、単なる衝突ではなく、働きかけや制御と見ることができます。五行は単純な善悪だけではなく、自然の調和や変化のしくみを表す深い思想なのです。